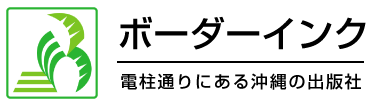『風の棲む丘』
湧上アシャ
46判 368頁
フェンスが分断した街で繰り広げられる
運命と決別の物語
俺たちは風の棲む丘で育った。
いつかここから飛び立つために−。
すべてが手に入るこの街で、島の未来だけが見つからない。
過酷なストリートを必死に生き抜く〈境界線上の子どもたち〉が織りなす運命の出会いと決別の物語。
ヒップホップ、レゲエなどストリート文化に影響を受けた沖縄の若き書き手が
フェンスで分断された街を舞台に書き下ろした長編青春群像小説。
本文より
黄昏の街
「気がつくと、いつも夕暮れだったの」
麻里・ジェーン・フイッシャーは、暮れゆく街を見つめたままそう言った。それから隣に座る神谷海の口から煙草を奪って、自らの唇に寄せた。
「どういう意味?」
麻里は応えない。褐色の肌に映える切れ長の目を細めて、薄く笑うだけだった。
「ま、いいけど」
諦め口調で海はそう言って、新しく煙草を取りだして火をつけた。吐き出された白い煙が、夕焼け空へとのぼる。
ここは、丘の上にある街。ふたりは並んで公園のフェンスに腰かけ、南風に流されていく夕焼けを眺めていた。すこしずつ街に明かりが灯りはじめ、風が冷たくなる。
「……この時間にようやく目が覚めるのよ。世界なんてものに価値はない。けれど、なにも影響を与えられない自分のほうが、価値がない。そう気づいた時には、太陽は逃げてしまう。いつだって、見送ることしかできない」
「すこし、わかる気がする」
「……ありがと」
遠くから、公民館のチャイムが聞こえてきた。鉄琴の音が鳴りやんで、海が申し訳なさそうに口を開いた。
「あー、そろそろ」
「帰る?」
「うん」
「そう」
麻里は表情こそ変えなかったが、言葉に残念だという響きがこめられていた。麻里はフェンスから飛びおり、歩き出した。海もあわてて後を追う。
「麻里、明日は学校来いよ」
「どうして?」
「どうしてって、おれたち受験生じゃないか。お前頭いいんだからさ、今からでも高校いけるって」
「わたしの勝手じゃない」
麻里は中学一年生のころ、テストで学年一位を取りつづけた。さらに全国一斉模試で、県内で上から三番目の成績を残した。そしてその年の春、彼女は学校に行くのをやめた。
ずんずん先に進んでしまう麻里に、海はついていくので精いっぱいだった。まるでふたりは競歩でもしているのかという速さだった。強い風が吹いて、腰まである麻里の長い黒髪がなびいた。
「子どもは嫌いなの」
「子ども?」
「そう。子どもはいつだって嘘つきと弱いものをいじめたがるのよ。そして異端児や天才を虐待するの」
海は、なにも言えなかった。麻里はアメリカ人と日本人の両親を持つ。日本人ばかりの教室にその色の肌は、それだけで目立つ。さらに頭がよくてひねくれ者。男子生徒にはわりと人気があったが、女子生徒の妬み嫉みを買うこともすくなくはなかった。
「なんだよ。嫌がらせでもされてるのか?」
麻里は立ちどまり、軽蔑の目で海をにらみつけた。しかし、怒鳴りつけることはせず、ひと呼吸置いてからこう言った。
「わたしの人生だから」
海はしばらくあっけにとられたが、みるみるうちに笑顔になっていった。麻里の人間性を垣間見た気がしたから。
「へー、かっこいいね」
それは単なる感想なのだが、麻里には冷やかしに聞こえたらしく、また先に歩き出してしまった。
「まてよ。じゃあ、公園には顔出してくれよ。な。おれたちいつもここでバスケやってるから」
「バスケ?」
「バスケット。バスケットボール。麻里が来てくれると、四人になるからツー・オン・ツーできるんだよ。運動、嫌いじゃないだろ?」
「嫌いじゃないけど……」
「よし、決まり。あ、麻里そっちから帰るの? おれんちこっちなんだよ」
そもそも今日は、麻里が学校をさぼって公園で読書をしているところを、海が声を掛けてきたのだ。
「明日、楽しみにしてるからな」
「気がむいたらね」
「気がむけよ。絶対!」
大きく手を振って、海は坂の上に駆けていった。白いシャツを、傾いた陽ざしが橙色に染めていた。
●目次
プロローグ 春の空
黄昏の街
境界線上の子どもたち
国境なき少女
傘の中の宇宙
別れ
沈黙の青 激情の赤
苦しみの種、喜びの花
雷鳴
月虹
街角
暴風警報
路上の花
群青
一本の槍
靴磨きの少年と花売りの少女
だれも見つけられない
旅
すべては明日の光を見るために
著者略歴
湧上アシャ
1990年沖縄県宜野湾市普天間生まれ。普天間高校出身。
17歳から本格的に小説を書きはじめる。ふたつの大学に進学するが、どちらも中退。2016年10月から、同人サークル「タフコネクション」に参加する。ヒップホップやレゲエの文化に強い影響を受けており、ラップしたり、イラストを描いたりもするが、文章をメインに活動中。