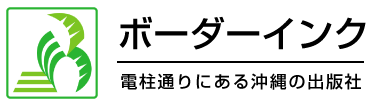--------------------------------
A5判 上製本 202ページ
定価 3,080円(本体2,800円+税)
池宮喜輝
--------------------------------
令和の世へ、琉球の芸能をこよなく愛した三線演奏
家が贈るメッセージ。
18世紀初頭に始まったという沖縄の芸能「組踊」
唱えと音楽と踊りからなる歌舞劇で1972年に国の重要文化財に指定され、2010年にはユネスコ無形文化遺産となった。
その組踊が「国劇」と称されていたいた時代
組踊をはじめとした伝統芸能の未来を案じた三線演奏家の著作集。
著者は1915 年(大正4)、金武良仁、伊差川世瑞らとともに沖縄音楽最初のレコー
ドを出し、1936 年(昭和11)6 月、琉球芸能の東京・大阪公演
にに参加して音楽を担当。著書に『三味線宝鑑』(1954)などがある。
本書は自筆原稿を中心に新聞や雑誌に掲載された原稿を参考とした。
*第二弾『琉楽・三味線』、第三弾『瑞泉庵の日々』発刊予定
●目次
口絵 琉球古典音楽家・池宮喜輝(1886〜1967)アルバムより
凡例
第一章 国劇・組踊の歴史
琉球の国劇「御冠船踊」
玉城朝薫年譜
組踊と古典舞踊の歴史
沖縄郷土芸能について
尚敬王代に始まる冠船踊と記録
琉球国劇の復活を提唱
文化財と組踊保存会
第二章 組踊の見どころ聴きどころ
組踊の見どころ聴きどころ
「出ようちやるものや」について
「手水の縁」(断章)
座談会 組踊「大川敵討」をめぐって(抜粋)
組踊「大川敵討」上演について
歌学・歌道・音曲について
明治以後の組踊
第三章 組踊の地謡
『地謡 必携組踊声楽譜附 工工四』序
組踊と音楽
組踊地謡のこころ
琉球組踊保存会『地謡』心得
琉球地謡心得
琉球古典舞踊七踊
第四章 創作舞踊・劇
創作舞踊「仏教音芸」
創作劇 「琉球歌聖 知念績高出世物語」
解題 歌三線を中心にした楽劇 田場裕規(沖縄国際大学教授)
本書の出典・参考資料
あとがき
●本書「解題」(田場裕規)より抜粋
古典とは何か。古典文学、古典芸能等、古典を冠した用語には、価値観を統合する意識とともに、次世代に継承することへの情熱が見出される。古典化は、価値と継承に対する人々の意志として理解することができる。文学も芸能も、出現したときは、イマの文学であり、イマの芸能であった。しかし、時の流れの中で、価値が見出され、敬意と愛情をもって次世代へ継承されていくうちに、古典化されていく。古典とは、単に古いもののことを指さない。長い時間をかけて、人々の価値観が形式となって現れ、その形式に敬意と愛情を見出すことによって出現したものといってよいだろう。
「琉球古典芸能大会」は、歌三線のみが古典を意識していたと考えても良いかもしれない。とりわけ、池宮喜輝は、歌三線の心を組踊に見出していた稀有な芸能家だった。本書には、池宮が、古老や師匠方の口碑や実演場面で定着していった型などについて、細かな注釈とともに収載されている。それは、組踊への敬意と愛情が池宮をつき動かしたと言っても過言ではない。「琉球古典芸能大会」は、まさしく、組踊の古典化の画期であったことを裏付けるものである。
●著者プロフィール
池宮 喜輝(いけみや きき)
1886年(明治19)那覇市若狭町村に生まれる
1904年 桑江良慎の高弟・我謝秀益師に入門し本格的に三味線の道へ
1915年(大正4)金武良仁らと沖縄音楽最初のレコードを出す
1924年(大正13)野村流音楽協会創立(会長伊差川世瑞)副会長に就任
1928年(昭和3)「絃声倶楽部」を結成し、後進の指導にあたる
1929年(昭和4)県議会議員に当選
1936年(昭和11)東京で開催された「琉球古典芸能大会」に出演
1944年(昭和19)宮崎県に集団疎開
1945年 九州で終戦を迎え、1947年疎開先の九州から川崎市に転居
*池宮城姓を池宮に改姓。
1948年東京沖縄芸能保存会を東恩納寛惇らと結成(会長:比嘉良篤)
*川崎市中島町において野村流の指導を行う。東京での公演などに出演
1951年 ハワイと北米に渡り音楽の指導と三味線調査を行う
1952年 野村流音楽協会第五代会長に就任(1963年3月31日まで)
1954年『三味線宝鑑』を出版
1956年 琉球政府文化財保護委員、無形文化財の専門委員を拝命
1957年 高野山、比叡山を訪れ、声明と琉球古典音楽の関連調査を行う
*川崎から沖縄に戻る
1958年 古希記念の『琉球百人一首』と『琉球の狂歌』を出版
1961年 沖縄タイムス賞(文化功労賞)受賞
1963年 『演奏用・分類解説 琉歌集』を出版
1963年 ハワイや南米の支部の招きで指導へ。1964年4月帰沖
1967年 死去(7月22日)
1982年 野村流音楽協会により、沖縄市民会館前に顕彰碑建立
1987年 『琉球芸能教範』(月刊沖縄社)発行
2004年 国立劇場おきなわの組踊先達顕彰碑に刻銘
●初版発行
2025年4月