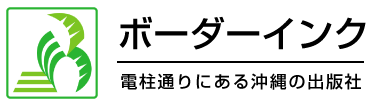-----------------------------------------------
●46判 224ページ
●定価1980円(本体1800円+税)
●南ふう著
-----------------------------------------------
首里城に感じた違和感とは何か
首里城の方位の謎に迫るノンフィクション
「なぜ首里城の浮道は少し斜めになっているのか?」
違和感解明のために本を読み、ネットを検索し、現地へ行き、友人知人からインスピレーションをもらい、道草を楽しみながら自分なりの説へとたどり着いた。
本書「はじめに」より
(前略)
奉神門をくぐると、正面に正殿がある。そこへ向かって伸びる一筋の道が浮道。つまり浮道は奉神門と正殿の中央を一直線に結んでいる。だが奉神門・南殿・正殿・北殿の四棟に囲まれている御庭をあちこち歩いているうちに、「あれ?」っと思ったのだ。正殿正面に立っているはずなのに、浮道がまっすぐこちらを向いてない。奉神門を入った時には正殿に向かって伸びていたはずなのに? そう、正殿と浮き道は直交していない。
だが「変だな」と感じたものの、どの方角にどれくらいずれているのかを考えるには至らなかった。が、直交している方が美しいはずなのに、なぜそうではないのかという疑問は、いつも何となく頭の片隅にあった。それは若い頃グラフィックデザイナーをしていたこともあって造形への関心が高いのかもしれないし、できれば謎を解いてみたいという探偵気質的な性格のせいなのかもしれない。
積年の疑問を解決したいと執筆を始めたのは二〇二二年だった。これまで漫然と感じていたこと、あれこれ断片的に拾ってきたこと、それらを文章にしていく過程での取材を通し、何かが見えてくるかも知れないと思ったのだ。
言い換えれば、これは私の紆余曲折の旅の物語でもある。
●目次
はじめに
第一章 直交しない正殿と浮道
浮道は東西軸 /首里森御嶽のない絵図 /首里城はいつ建てられたのか /
風水思想で西向きを考える /弁ヶ岳の三角点 /十八世紀の地図
第二章 古代日本人の東西軸重視
『知られざる古代』を読む /「東西」にこだわる日本人 /日置という一族 /
琉球王国のヒキ /大陸と船のつながり /沖縄では北がニシである /
今帰仁にあるピラミッド /太陽信仰 /日置とヒキ
第三章 正殿の焼失
首里城炎上 /再度弁ヶ岳の線を探る /正殿の大龍柱 /
あちこちに見る龍柱 /増える首里城の特集 /大龍柱の向きと浮道の屈折 /
朝拝御規式での肌感覚 /南方重視から北方重視へ
第四章 磁北と真北
軽石の漂着と海図 /伊能忠敬の大日本沿海輿地全図 /中国における条里 /
十五世紀の那覇の偏角 /緯度と経度 /経度は時間、時間は経度
主要地点との角度を探る
第五章 正史に触れる
まず『球陽』 / 『中山世鑑』と『中山世譜』 /冊封使が記した航路 /
台湾の富貴角 /古代中国の測量 /建物の向きの意味 /
すべてが記録されるわけではない
第六章 二つの基準と大龍柱
二つの基準 /違和感の緩和策 /階段と大龍柱 /
最古の写真より前の大龍柱 /首里城復元に向けた技術検討委員会 /
明治末期の龍柱 /狛犬の誤解 /『火難の首里城』を読む
第七章 更新される情報
時代によって違う北極の星 /「禹跡図」との出合い /角度を追い求める /
デジタルアーカイブの威力 /中国の検索エンジン /素人の限界 /
ずれの角度の再考 /風水師の新解説
第八章 終わらない探索
富貴角に行く /ネット記事との出合い /被葬者の頭位方向 /
枯れない泉『知られざる古代』 /宮城島を歩く /墓の向き /
ルーツを求める人たち /まとめにかえて
参考文献・資料・メディア・ウエブサイト
あとがき
●著者プロフィール
南ふう(みなみ ふう)
本名:浜田京子
1974年 県立那覇高等学校卒業
1978年 国立九州芸術工科大学 環境設計学科 卒業
1978〜1980年 株式会社国建設計開発部勤務
1980〜1998年 関西にてグラフィックデザインを経験
1999〜2016年 株式会社渡久山設計総務部勤務
2016〜2022年 沖縄県公文書館内で「琉球政府文書デジタルアーカイブ」に従事
・2003年 長野県阿南町主催「第1回祭り街道文学大賞」にて『女人囃子がきこえる』で大賞受賞
・2010年 沖縄市社会福祉協議会主催「第19回ふくふく童話大賞」にて『クモッチの巣』で大賞受賞
●2025年6月発行