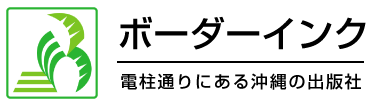私たちの教室からは 米軍基地が見えます
普天間第二小学校文集「そてつ」からのメッセージ
渡辺豪著 B6判ソフトカバー 192頁
「世界でもっとも危ない基地」米軍基地である普天間飛行場と隣り合わせの、普天間第2小学校に通う子ども達は、切実な思いを、学校の文集「そてつ」に綴った。大人になった彼らは、いま何を思うか。
「そてつ」は、沖縄の日本復帰の翌年から刊行されている小学生たちの思いを綴った文集だが、やはり「基地」に関するものが目をひいて多い。沖縄タイムス社記者・渡辺豪は、作文を書いた子どもたちのその後の人生を追い、インタビューを重ねた。「動かない基地」の現実を当事者の言葉で見つめたそのルポルタージュは、今年四月から五月にかけて「基地の街の子」として連載された。さらに追加取材を続け、新たな視点でまとめなおしたのが本書である。
等身大の「普天間問題」に触れる、渾身のルポルタージュ。
「私の住む沖縄」
ぼくたちの住む沖縄は、
とってもとっても小さい島。
青い空 い海
これに調和して
一年中変わらぬ緑。
このすばらしい自然の美しさは、
ぼくたちの自まん。
でも、悲しいことに
小さい島の大半は、
軍事基地で占められている。
すばらしい所は、フェンスで囲われ、
そこにゆうゆうと基地がそびえたち
主であるはずの沖縄の人たちは、
その片すみで、ほそぼそと
身をよせあっている。
ぼくたちの学校も
マリン基地と、となり合わせ
運動場をフェンスで区切られ、
向こうの基地は、ばかでかく広く、
ぼくたちの運動場は、
運動会もできないほどのせまさ。
飛行機は一度に何機も
校舎すれすれに飛び交う。
「ゴオウ、ゴオウ。」
ものすごい音を立て、
ぼくたちをいらだたせる。
先生の声がきこえず、勉強が中断される。
大きな基地に向かって、
「出て行け。」と、どなる。
しかし、
ゆうゆうたる基地は、
びくともしない
今も頭の上を
飛行機が飛んだ。
(1977年度「そてつ」より)
前書きより
宜野湾市立普天間第二小学校は、沖縄の本土復帰の翌年に当たる一九七三年度から毎年、在校生の文集「そてつ」を発刊している。同小は普天間飛行場と隣接し、敷地の境界が基地のフェンスという苛烈な環境に置かれ続けている。文集のタイトルにはこうした逆境を乗り越え、岩をも貫いて生きる蘇鉄のようにたくましく育ってもらいたい、との願いが込められている。
「そてつ」と向き合うきっかけは、二〇一〇年五月四日の鳩山由紀夫首相の来県だった。鳩山首相が普天間飛行場を「最低でも県外」へ移設する方針を断念し、「県内回帰」を地元に伝える対話集会の場として普天間第二小の体育館が選ばれた。筆者も取材のため立ち会い、そこで忘れ難い光景に出くわした。
入り口に金属探知機が設置され、大勢の警護が控える物々しい会場。重苦しい空気をはねのけるように、普天間第二小の教諭が威勢よく発言を求めた。
「騒音による昨年度の授業の中断は実に五十時間。それだけの時間を七百人余の子どもたちが奪われている。墜落したときにどのように子どもたちを守ったらいいのかと、いつもヘリを見上げている。一日も早い閉鎖を」
そう訴えた後、教諭はつかつかと鳩山首相に歩み寄り、児童たちが書いたメッセージを手渡そうとした。報道関係者のカメラのストロボやライトが集中し、警備が一斉に飛び出して制止する中、もみくちゃにされながら、教諭は子どもたちの声を首相に託した。
対話終了後、その教諭からコメントを得ようと、記者たちが取り囲んだ。筆者も加わったが、そのときふと頭をよぎったのが、第二小の文集だった。確か、同小独自の卒業文集のようなものがあったはずだ。ローカルのニュースで見た記憶がある。過去の分も含めて通読してみたい、と思った。
後日、同小の知念春美校長の許可を得て、数週間かけて過去の「そてつ」を全部読ませてもらった。子どもたちの日常生活をリアルに切り取った、きらりと光る、印象深い言葉が並んでいた。何より、「そてつ」というタイトルがいい。予想した通り、毎年必ず「普天間基地」をテーマに取り上げる児童がいた。当たり前のことだが、地元の人たちにとって、「基地被害」は九六年の日米の普天間返還合意後に始まった問題ではない。九六年というのは、全国メディアが「普天間問題」というかたちで「ニュース」として発信し始めた年であって、地元住民には単なる通過点にすぎない。
基地問題に関しては、日本本土と沖縄の認識のギャップがたびたび浮上する。しかし、沖縄県内でも、基地が集中する本島中北部とそれ以外の地域では、基地問題に対する受け止めに温度差がある。県内外を問わず、「当事者以外」の人たちに共感してもらう術はないか。生活者の視点から基地を語ってもらうことで、「等身大の世論」に近づけるのではないか。そのためには、小学生時代の詩や作文の紹介にとどまらず、「基地の街」で育った子たちが大人になった今、「動かぬ基地」に何を思うのか、じっくり腰を据えて聞く必要がある。そんな思いからインタビュー取材を始めた。彼らの基地との関係は、思想でも政治信条でも研究対象でもない。「親基地」「反基地」で単純に色分けできるものでもない。生活の中に基地が溶け込んでいる人たちである。普天間問題の当事者ともいえる人たちの心のひだに触れることで、複雑な心情を理解し、関心を深めてもらうきっかけになれば、と願っている。
担当編集より
■今この瞬間も、子どもたちが駆け回る校庭のすぐ真上を米軍機が飛び交っている。その現実に抗う言葉が本書には散りばめられている。収録された子どもたちの作文には、まっすぐな思いで見た基地と沖縄の現実があり、大人になった彼らの言葉には、「いつか、きっと」という希望が込められている。「生活者の視点」から基地を語ってもらうことによって、動かない沖縄の基地問題の本質が浮かび上がってくる。
渡辺豪(ワタナベ ツヨシ)
1968年兵庫県生まれ。関西大学工学部卒。毎日新聞社記者を経て98年から沖縄タイムス社記者。現在、特別報道チームキャップ兼論説委員。主な著書に『「アメとムチ」の構図〜普天間移設の内幕〜』(沖縄タイムス刊)、『「国策のまちおこし」〜嘉手納からの報告〜』(凱風社刊)
2011年10月 刊行